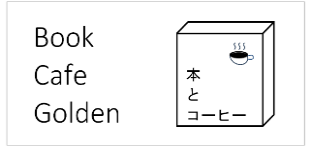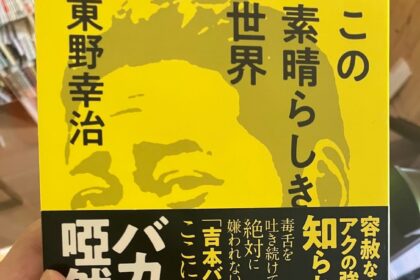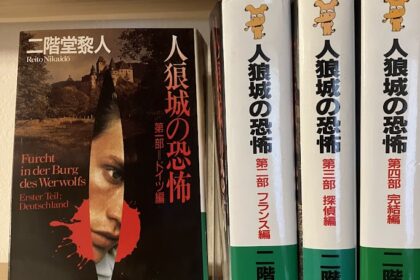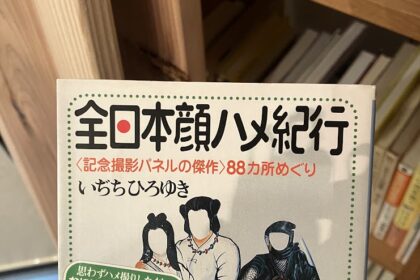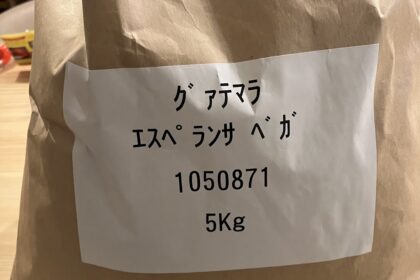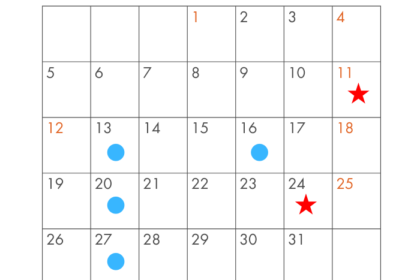仏像本「仏像のひみつ」
仏像が好きです。
最近けっこう落ち着いていますが一時期ドハマりしておりまして(奥さんも)、仏像の展覧会やら博物館やらお寺やら色々と見に行ったりしていました。
他にもガチャガチャで仏像シリーズがありましてこちらも集めていました。
↓はちょっと神仏習合しちゃってます。

仏像の本、仏教の本についてもいくつか読んできました。
そのためコロナ禍の際に”三密”という言葉が出てきたときは、コロナでどうしようもないから大日如来様と一体化を目指そう!というスローガンかと思ったのは冗談ですが(三密とは密教の考え方で身密、口密、意密という3つを行う修行)そのくらい仏像が好きです。
仏像の本で読んできた中でも今回ご紹介する本「仏像のひみつ」はわかりやすいのでおすすめです。
著者について
著者・山本勉さんはもともと東京国立博物館に努めていらっしゃった方です。
東京国立博物館はたくさんの仏像を所蔵しており、本でよく紹介されるような有名な仏像もあったりします。
あとがきに出てくるのですが、2005年に東京国立博物館で開催された「唐招提寺展 国宝 鑑真和上像と盧舎那仏」の展覧会は著者が手掛けた展覧会だったそうです。
非常に好評だったようで、それがきっかけになりこの本も出版にもつながったようですね。
この「唐招提寺展 国宝 鑑真和上像と盧舎那仏」の図録についてもお読みいただけるようにこの本の隣にでも置いておこうと思います。
仏像のひみつ
この本は以下の4章で構成されています。
- 仏像たちにもソシキがある
- 仏像にもやわらかいのとカタイのがいる
- 仏像もやせたり太ったりする
- 仏像の中には何かがある
いくつかこの本のポイントがあるのですが、まず一つ目のポイントです。
この本はあんまり細かい部分は省いてくれています(例えば印の名前とか)。
仏像や仏教の本というのは初心者が読む本とされている本でもけっこう知らない言葉が出てきて、そこまで興味がない人にとってはちょっとつらいかもなんですよね。
そういったひっかかりがこの本にはありません。
それでいて内容については押さえるところはしっかり押さえてあります。
そこでポイント二つ目です。
この本を読んで「お!?」っと思ったのが、”仏像もやせたり太ったりする”のところで書かれている時代ごとの仏像の体形の変化についてです。
よくある説明だと時代ごとに仏像様のお顔がこういったお顔ですよというのがあります。
それがこの本では上部から見た際の体形によって時代の変遷がわかるという説明があります。
仏像についてちょっと知ってるぜという人にも新たな視点を与えてくれる内容にもなっているんですね。
身近な仏像
さて、最後に身近な仏像様について書いておきたいと思います。
大都市の都心だと少ないかもしれませんが、少し離れるとたいていは道のわきなどにお地蔵様がいらっしゃったりします。
このお地蔵さんが一番身近な仏像様です。
正式には地蔵菩薩で菩薩様です。
同じ菩薩の仲間である弥勒菩薩様は56億7000万年後に出現すると言われているのですが、それまで仏様が世にいない状態となるため、その間救ってくださるためにいらっしゃるのが地蔵菩薩様ということになっています。
とても優しい仏像様なので見かけられた際にはぜひお手をあわせていただけるとと思います。
また、日本では地域によっては観音信仰が根強い地域もあります。
そう考えると仏像ってとても身近なものだったんだなと思います。
この本もお店がオープンしたら読めるようにしますのでその際にでもぜひ。
読書メーターにも登録していますのでこちらもよろしくお願いします。
https://bookmeter.com/reviews/126587736
次回はカウンター席の椅子について書きたいと思います。
ここまでお読みいただきましてありがとうございました。